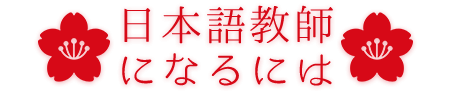歴史的背景
北海道の歴史的背景から説明していきます。
北海道方言は大きく分けると海岸部方言と、内陸部方言の2種類が存在しています。
方言というと地域ごとに分かれているイメージがありますが、土地によってはそれほど細かく分かれていないという特徴もあり、北海道の方言は日本語教師にとっても特別な方言である場合が多いです。
また、方言の誕生についてですが漁村で用いられるものが多く残っています。
逆に内陸部方言は共通語に近い特徴があるため、簡単に北海道方言を学びたいのであれば内陸部方言から入ると良いでしょう。
北海道方言は難しいと言われています。
その理由ですが、先ほどの漁村で用いられている方言は、一般の人には聞き取りづらい場合が多いからです。
今の時代ではそのような背景もあり、漁村で住んでいる若者でさえ方言について正確な内容を知らないこともあります。
それと、方言の種類は少ないのですが、用い方に関しては地域によって微妙に異なる場合が多いです。
このような歴史的背景が北海道方言にはあります。
和人の進出
北海道方言ですが、日本語教師として学んでおきたいものに和人の進出があります。
そもそも北海道方言は、他の土地の方言とは違い北陸方言や近畿方言の影響を受けている部分が多いです。
というのも、北海道は北海道に居住を構えるようになった和人の定着が早かったからです。
古くは飛鳥時代までさかのぼるのですが、平安時代末期頃では東北地方より以北に和人が進出していました。
その頃から、方言に関しても漁村で用いられる方言との交流が盛んで、今のようなズーズー弁などが用いられるようになったのです。
北海道の歴史
北海道方言についてですが、古くから多くの人が用いていただけで、多くの関心があったわけではありません。
というのも、北海道に多くの人々が住むようになったのは、歴史上では明治時代になってからだからです。
北海道というと昔から多くの人が住んでいるイメージがありますが、元々は開拓を必要とする土地であったため、基本的に居住を構えていた人々というのは開拓のために、北海道に渡った本州の人々だったのです。
入植者の割合では、東北地方出身者が4割ほど、そして北陸地方出身者が2割ほどとなっています。
また、過去の北海道では方言自体もそれほど珍しくはなかったため、方言のことを共通語だと誤認されていた人も多かったのです。
北海道では、このような現代では見られないような方言の歴史があります。
そのため、地域によっては北海道の方言についても正確にまとめられておらず、情報が錯綜している土地も多いという、北海道ならではの特徴まで存在しているのです。