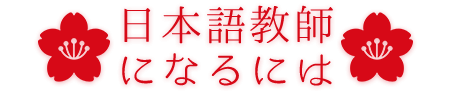関東弁
日本語教師がレッスンを行う方言に、関東方言というレッスンはあまり見かけません。
その理由ですが、関東弁として親しまれている場合が多いからです。
方言をわざわざ日本語教室で習う理由は、1つは興味、もう1つは歴史を学びたいという意欲が存在するためです。
ですが、それほど難しく考えなくても関東方言に関しては独学で学べるような内容でとなっています。
例えば、語尾に「べー」を付けるだけでも関東弁らしくなるため、これといって特徴らしい特徴があるわけではありません。
その代わり、アクセントや使われている地域に関しては細かく分布しているため、知識の1つとして学ばれている人が多いのです。
関東弁を日本語教室で学ぶ際ですが、注意すべきは分布のほうでしょう。
というのも、方言にしては珍しくそれほど用いられることがなくなっている方言だからです。
例えば、東北方言の場合は北奥羽方言や南奥羽方言があり、分布に関しても関東や東北にかけてとなっています。
そして、今でも高齢者であれば先ほどの「べー」のような特徴的な方言で会話されていることが多いです。
しかし関東弁は「共通語」を通じた会話が目立つ現代では、過去のものとして扱われている状況にあります。
また、方言にしては珍しく一部の人が好んで用いている方言でもあるので、そのような要素(背景)のほうに注目が集まっていたりもするのです。
方言としてではなく、むしろ文化コミュニケーション上で必要となることがある程度・・・という認識が方言の理解では正しいでしょう。
総称として用いられている
関東弁を簡潔にまとめると、「べー」を用いる。
そして「アクセントは強まる」という特徴のみが際立っています。
言い方を悪くすると、特に個性的な方言となっている部分が見当たりません。
また、関東方言は大別すると東関東方言、西関東方言があるくらいです。
そのため、地域によって他の土地の方言を吸収し、多様性が見られる方言となっているわけでもないのです。
北海道方言では、東北地方だけでなく北陸地方の影響も受けて、歴史の中で方言が完成していったという事実がありますが、関東方言は関東弁の総称で知られているもののとおりで、これといって歴史的な背景もあり誕生したという説が見当たらないのです。
このような特徴が関東方言にはあるため、若年層が好んで用いているということもありません。
今では圧倒的に共通語を元にした会話が多く成立しているため、部分的に方言を用いるというわけでもないのが関東弁の特徴と言えます。
日本語教師から学ぶ際も、基本的にどのような歴史があり、またアクセントの付け方はどの程度なのか・・・という簡素な内容で授業を受けることが多いでしょう。