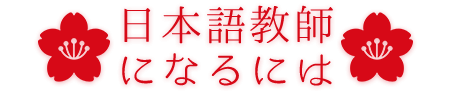日本は最古の歴史のある国です
日本語は世界でも有数の難易度の高い言語体系をしていますが、その理由の1つが「日本」という国の歴史の長さです。
日本は四方を海に囲まれた島国ですが、その中で国と呼べる民族の集団が生まれたとされる最古の記録は紀元前660年の2月11日とされています。
これは世界で最も古い記録として残されており、実際に国として機能をし始めたのは4世紀ころを言われてはいるものの世界第二位とされているデンマークの建国が10世紀頃とされているので、いかに古くから国として機能をしてきたかということがわかります。
歴史が古いということはそれだけ長く文化が培われてきたということでもあります。
日本最古の書物とされているのが「古事記」ですが、これができたのは712年といいます。
つまりその頃までには既に私達が現在使っているような日本語としての言語体系のもとになることがすでにしっかりと構築されていたということになります。
日本語は世界最古の言語?
では言語も世界で最初にできた言葉なのかということになりますが、それについては諸説があるようです。
日本語はどのようなルーツを経て日本国内に入ってきたかということは、「アルタイ語族説」「朝鮮語同系説」「高句麗語同系説」「百済語起源説」など非常に多くの説が数多くの言語学者によって唱えられています。
諸説があるとはいえ、日本語という言語が世界中に存在する言語の中でも抜きん出て複雑な構成内容になっているということは事実です。
それは数多くの言語が別のルーツから日本に入ってきて、それが狭い島国の中で咀嚼され別の形として生まれ変わったということを示しています。
日本語の特徴のもう一つとして挙げられるのが、書き言葉が非常に煩雑なしくみをしているのに対し、声に出して発音をするときの音の数が多言語に比べてかなり単純にできているということです。
実際日本語の習得を目指す外国人などは、読み書きができるようになるまでにはかなりの時間がかかる一方で、会話ができるようになるのはそれほど難しいわけではないといいます。
世界の他の言語ではむしろ逆に発音をする音の数は多いのに、表記する文字数はかなり少ないということもよくあります。
日本語の複雑さは優れた詩歌のため
なぜこのような世界的な言語の流れと正反対のことが起こっているかというと、それは日本の代表的な文学作品を見た時にわかります。
日本には俳句や短歌など短い言葉の中に細やかな意味を込めた文学作品が多くありますが、文字にしたときの複雑さはこの詩歌表現をするために非常に適したものです。
日本語独特の言語的特徴である「オノマトペ(擬声語)」も、詩歌における表現のために自然にできあがったものとされています。