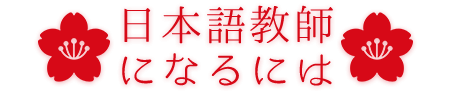九州弁
日本語教室では東北方言、中国方言、そして九州方言を学ぶ人が多いです。
かなり個性的な方言となっているため、講師陣も正確に地域の歴史や発音について教えてくれることも多く、また現代でも用いられていることの多い方言とされているため、積極的に独学されている人まで多く存在します。
九州方言は俗に九州弁(きゅうしゅうべん)と言われている方言のことです。
九州弁を用いる土地は、大きく分けると豊日方言・薩隅方言・肥筑方言で分類することができます。
学者によっては、九州弁を西日本方言に含めている人もいるほど、多岐にわたる構成となっている方言でも有名です。
理解できない発音が多い
九州弁の最大の特徴は聞き取りづらい点にあります。
方言というと、その土地に住んでいない人の場合は聞き取れないものが多いという解釈が目立ちますが、実際はそれほど多くありません。
例えば、「~やん」や「~じゃ」という方言も存在するのですが、「~します」と大きく違いませんし、文章上でも理解は難しくありません。
他にも、「~キニ」という表現も四国方言では用いられているのですが、前述と同じで文章上では「~します(~だ)」という表現であることが分かりやすいです。
このように方言というのは理解することが極めて難しい・・・というわけではなく、最低限の文法・用途を知っているだけで理解可能なのです。
ですが、九州弁は同じように理解するのは難しい方言だと理解しておきましょう。
例えば、「犬」は「いん」。
「秋が」は「あっが」のような発音となりますので、語尾ばかりに注目されても文章を理解できないことがあるのです。
他にも理解し難い方言では以下のような方言があります。
狼(おおかみ)のことを「うーかみ」。
今日(きょう)のことを「きゅー」と発音することもあるため、会話全体で理解が必要な方言という点が、一般的な方言と大別できる部分です。
強調する発音が多い
九州弁の発音には個性的なものが多く存在します。
例えば、「すごい」という表現では「すごか」という発音が良く用いられます。
また、このように特徴的な発音が目立つため、部分的には理解している人も多い方言なのです。
例えば、「~できない」という断定を含む会話では、「~きらん」が用いられます。
そのため、「お腹がいっぱいでもう食べられない」という表現では、「お腹がいっぱいでもう食べきらん」という表現が用いられるのです。
ただ、このように複雑な内容となっている九州弁ですが、他の方言と似通っている部分も多く存在します。
断定助動詞の「じゃ、や」といった表現。
他にも、否定助動詞では「ん、おる」という表現が用いられているのです。
これらの表現は、「中部地方・近畿地方」でも頻繁に用いられている表現とされています。