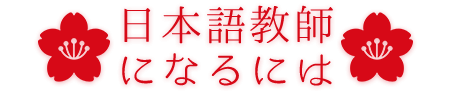東北方言に近い
日本語教室では東北方言の人気が高いです。
その理由は、中部方言(ちゅうぶほうげん)のような特殊な方言となっているからです。
アクセントについてですが、日本語教師の発音を真似て覚えることが多いでしょう。
個人で発音の練習をされていても、抑揚をきかせて発音するのが難しい部類のためです。
中部方言は、方言が使われている地域(全域)で東京式アクセントとなっているのですが、地域によっては微妙に違う発音を用いることもあります。
そのため、今では比較的発音がまとまっている地域で、「ギア方言、ナヤシ方言、越後方言」とまとめられていることが多いです。
また、このようなアクセントの違いだけでなく、中部方言や東北方言については北海道方言に影響を与えているという歴史も存在します。
明治時代以降になると、北海道の入植者も多く増えていったのですが、中部・東北とは交流が盛んであったため、方言の上でもこのような影響を受けている時代があったと記されているのです。
独特な表現を用いる
中部方言ですが、共通語に似ているようで似ていない表現が目立ちます。
例えば、「魚がいる」という言葉は中部方言では「魚がおる」でも成立するのです。
他にも、「魚がいる」という言葉は「魚がおるん」でも成立する場合があります。
このように1つの表現(区切り)に対して、地域によって言葉の使い方が違っているという特徴があるのです。
これは中部方言だけの特殊な表現方法とされています。
アクセントについても、語尾を持ち上げるように発生するものと、逆に完全に区切って発音するために声のトーンを下げるものまであります。
発声に関して、地域レベルで事細かく違っているのも中部方言だけの特徴でしょう。
それと、断定の際も中部方言では「じゃ・や」などが用いられます。
具体例では、「もう少しで12時になります」という表現は「もう少しで12時じゃ」というふうに表現するのです。
全体的に見ても高齢者などが自然に発生してしまう表現が多いため、高齢者の会話と方言の区別が付きにくいという特徴もあると理解しておきましょう。
今も使われている
中部方言は、地域レベルで今もなお使われている方言であるというのが最大の特徴です。
例えば、東北方言・北海道方言といった歴史的にも長い文化を誇る方言というのは、今では高齢者のみ用途について理解しているという現況のため、若年層が使っている割合はかなり低い状況です。
しかし中部方言は、「~じゃ、~なん」といった日常に溶け込みやすい発声のものが多いため、若年層も知らずの内に使い続けているという特色があるのです。
方言を学ばずとも学んでいる人が多いという点では、他の方言とは大きく異る方言とも言えるでしょう。