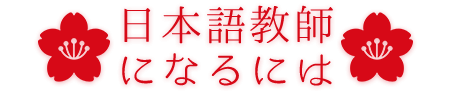摂津弁
近畿方言は日本語教師を通じて学ぶ上では、難しい部類の方言として知られています。
というのも、方言そのものに共通語との関連性があまり見られないからです。
一般的に知られている近畿方言は摂津弁(せっつべん)と言われるものでしょう。
例えば、「~です」は「~どす」となります。
この「どす」は京言葉としても知られているため、一般の人でも言葉の意味を理解するのは難しくありません。
現代では時代劇などを見ている人や、もしくは方言についての豆知識でも良く登場する言葉だからです。
また、このような流通の背景には大阪や京都との交流が多く、これらの土地から方言が複雑化していったという見方が強かったりします。
それと、摂津弁は播州弁の影響を受けてもいます。
そのため、独自色が強い方言としても知られているため、日本語教師の方も学ばれている方が多くいるのです。
近年では、語尾などに対して方言を用いる人はいますが、それ以外の方言については地元の方でも若年層では知らないという人が増えています。
そのような影響もあり、今では日本語教室を通じて過去の方言を学ばれている人もいるのです。
摂津弁は丁寧語に通じているものもある特殊な方言です。
例えば、「~とう」や「~よう」というテヤ敬語といった方言まで存在し、神戸弁と共通している特徴も多く見られるという特色があります。
ただ、他の方言と同じで一部地域ではそれほど利用者が見られないなど、昔に比べると頻繁に用いられる状況とはなっていません。
志摩弁
志摩弁も近畿方言の1つです。
志摩弁は、三重県の志摩市・鳥羽市・度会郡の南伊勢町で用いられることの多い方言となっています。
同じ近畿方言で種類分けがされていますが、志摩弁の場合はアクセントの差が地域によっても小さいという特徴があります。
そのため、伊勢志摩弁としても親しまれている方言として有名です。
近年では、テレビなどの影響もあり「おおきんな(ありがとう)」や、「おそがい、おとし(恐ろしい)」、他にも「~やがぃ(~だから)」といった方言が知られるようになりました。
三重弁
三重弁も近畿方言の一種です。
アクセントが京阪式となっているため、意外と多くの人が知っている方言であったりもします。
例えば、否定の言葉を用いる際に「~へん」や「~やん」という発声を行うのですが、これは他の方言では見られない独特な表現でもあります。
他の方言では、「~や、~じゃ、~ん」といったハッキリとした表現が多く用いらています。
ですが、三重弁の場合は「~やん?」のように否定を確定させるようなアクセントで、言葉を強調するような表現があまり用いられていないのです。
このような三重弁は、奈良県、和歌山県で良く用いられているという方言で親しまれてもいます。