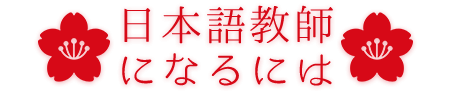用いられている県が限定的
四国方言は香川県、愛媛県、徳島県、高知県で用いられている方言です。
方言というと細かい地域にまで分布している場合が多いのですが、以下のように四国方言は決められた地域のみで流通しているという特徴があります。
例えば、北四国方言は「香川県・愛媛県(南部は除く)・徳島県」で用いられています。
南四国方言の場合、「高知県(西部は除く)」で用いられているので、広い範囲で分布しているわけではないのです。
そして、四国西南部方言では「愛媛県(南部のみ)、高知県(西部のみ)」で用いられている方言となっているのですが、詳細について分類した場合でも3種類で分別が行えるようになっている方言でもあります。
このような分類が可能なのですが、方言を全部で2種類と分別する方法や、高知県の方言のみ他にも種類があるという考え方も存在しますので、詳細を追っていくと、他の方言と同じで多分化しやすい方言となっています。
表現方法の多様化
四国方言ですが、似通っている方言が多いという特徴もあります。
例えば、四国方言は「近畿方言、中国方言、九州方言」との間で、多くの共通点が確認できます。
理由を説明する際の「~ケン、~キニ、~キー、~ケー」は、かなり特徴的な表現のように感じるものですが、実際は他の方言でも同じような表現が数多く存在するのです。
例えば、関西方面では「~ヤン、~ナン」のような方言が多く見つかりますが、用途は中国方言の「~ケン」と大きく違いません。
多様化している特徴がある方言ではあるのですが、中国方言は土地によって九州や関西地方の影響を受けている傾向が強いのです。
そのため、四国地方では東に行くほど近畿的な方言が数多く用いられ、西に行くほど九州的な方言が数多く用いられています。
四国地方の方言を他と分類する場合、「語彙」が他に比べて多いという点を良く理解されると良いでしょう。
現代でも良く登場する
方言の全体的な共通点として、若年層の理解者が大きく減ってきているという共通点が存在します。
関東から東北にかけて用いられている方言が該当するのですが、今では若年層がまったく用いていない方言まであるのです。
しかし、四国方言はその1つではありません。
現代でも「~ケン、~キニ」が良く用いられているのですが、地域でも交流が多い土地が多く存在するため、方言の存続が危うくない状況となっているようです。
実際にテレビでも四国方言は多く登場します。
発音そのものがしやすく、且つ地域によって通じない場合が少ない点が評価されているため、四国方言は日本各地でも知られるようになりました。
近年ではドラマの影響もあり、方言も含めて理解者が募っている地方でもあります。