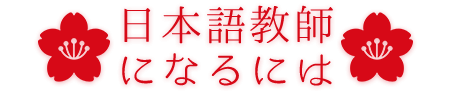山陰・山陽で分かれる
山口県・島根県西部(石見)、兵庫県北部(但馬)、京都府北部(丹後西部)、広島県、鳥取県東中部(因幡・伯耆東部)、岡山県で良く用いられている方言が中国方言です。
方言としては分類上、西日本方言に属している方言でもあります。
また、雲伯方言とは混同しないよう注意しましょう。
雲伯方言は島根県東部、鳥取県西部で良く用いられている方言なので、分類上は中国方言に該当しません。
しかも、音韻体系も大きく異なっているので混同しないよう注意が必要です。
中国方言の詳細
方言というのは、基本的に日本語教室を通じて学ぶことが多いです。
日本語教師の方も地域に属している人物、もしくは日本語の方言について試験を受けられている人が担当してくれるため、正しいアクセント(発音)を学ぶことができます。
ただ、方言のほとんどはアクセントにそれほどの癖がありません。
中国方言の場合も東京式アクセントで問題ありませんので、最低限のレベルであれば独学で対応することも可能なのです。
ただ、「のばして発音する」という特徴が地域では存在するため、日本語教室ではその点についても学べるようになっています。
中国方言の場合、「アイ」といった連母音が「アー」や「エー」となるだけではありません。
地域によっては、「ャー」と発音することもあるのです。
このような特殊な発音も用いるため、実際の会話練習でも「手紙を」の部分は「テガミュー(テガミョー)」と発音することも習ったりします。
中国方言以外の方言では、語尾を強調するような方言が目立つため、語尾について学んでいれば最低限の方言による会話が行えます。
ですが、中国方言の場合は「声の最後の部分をのばす」だけでなく、「キャー」や「キョー」と発音することが正しいもの、正しくないものまで存在するので、日本語教室に通わなければ区別が付かないものも多いです。
断定に独特なものが目立つ
前述のとおり、中国方言は山陽・山陰で分別できるのですが、簡単な分類としては「じゃ、だ」があります。
「じゃ」を用いるのは山陽。
「だ」を用いるのは山陰と覚えておきましょう。
他にも共通して似通っている部分も存在し、動作の完了は「~よる」を用いることが多いです。
そのため、「大雨が降ってきた」という表現では、「大雨が降ってきよる」という表現を用います。
この「よる」は他の方言では「嫌う」際に用いられる表現でもあるので、物事を避けて使われている「よる」なのか、それとも状況説明の「よる」なのかが区別しづらいです。
中国方言以外では、断定を意味する言葉に「~ん、~じゃ」などが良く用いられています。
そのため、中国方言と似通っているため区別が付きにくい表現は、意外に多かったりするのです。